第12回研究会 第53回マルチスピーシーズ人類学研究会 と共催 日時 2021年6月13日(日)13:30~17:30 場所 zoom (*申し込みはマルチスピーシーズ人類学研究会のサイトへ) 参与と生命 I 生きる場とともにたしかめる知を巡らせる 【趣旨】 人間という「単一種」が地球環境を破壊したとする「人新世」という今世紀初頭の問題提起に対して、人間によって支配・統御されてきた動植物や微生物などと人間との関係性を軸に「多種」の絡まり合いを主題化するマルチスピーシーズ研究が立ち上がった。マルチスピーシーズ研究は、その出発点から「生命」というテーマを胎んでいた。 私たちは人間である以上に、種である以上に、生命である。生命に「参与する(participate)/関与する(engage)」ことで、生命たり得ている。2021年度マルチスピーシーズ人類学研究会では、「参与と生命」というトピックを設定し、3回シリーズで研究会を開催し、隣接諸領域との対話をかさねながら、私たちが取り組むべき課題を探っていこう。 昨今、研究者として事物を対象化して論じるあり方に疑義が呈されている。その射程は理論家と実践家の従来のあり方を組み替える衝迫力を持つと思われる。そこで、第1回目として今回は、「生きる場とともにたしかめる知を巡らせる」と題して、人類学者、美学・芸術学者、比較思想家に話題提供してもらいながら思索を深めていきたい。 【プログラム】 司会進行:MOSA(マンガ家) 13:30~13:35 趣旨説明 13:35~14:25 奥野克巳(立教大学 異文化コミュニケーション学部 教授) 「『人間的なるものを超えた人類学』を進めてみて『生命』について人類学者が考えたこと」(仮) 14:25~15:15 増田展大(九州大学 大学院芸術工学研究院 講師) 「行き違うアニミズム──イメージ人類学、または物質に生じる思考について」(仮) 15:15~16:35 休憩 15:35~16:25 甲田烈(東洋大学 井上円了哲学セン...
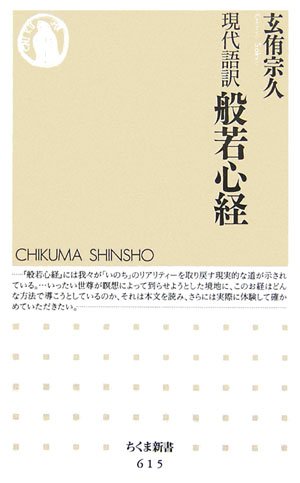
言葉を用いた理知的解釈は、生のリアリティを感じるには不向きである。理知的な分析知は、「全体性」を分断する。「全体性」とは、体験的に観ずるものである。理知によらないもう一つの体験的な知が「般若」である。「般若」の捉える「全体性」は、無常に変化する無限の関係性の中にある。「全体性」の実感を、老子は「道」、荘子は「渾沌」と呼んだ、それらは世尊と近似した実感だったため、仏教は中国にスムースに浸透した。
返信削除目で見たもの(色)を感覚(受)、知覚(想)により、特定の方向に気持ちが志向(行)し、脳の何らかの認識が芽生え、蓄積される(識)。識は人間が受胎の瞬間から持っているもので、その後、複雑に増殖する。この「五蘊」こそが我々人間なのであるが、それは全部「空」である。つまりあらゆる現象は、単独で自立した主体(自性)をもたず、無限の関係性の中で絶えず変化しながら発生する。つまり、「縁起」する。
「空」であるとは、「因果」(=異時)も「共時性」(=同時性)も存在することである。実相は「異時」と「同時」を含みながら、絶えず「流動」として消滅し続けている。それらを「相依性」とも言う。
六境(色声香味触法)が六根(眼耳鼻舌身意)に出会い、感覚器と能で把握するのが「色」であるが、人間が見ている姿だけが、物体の実相だとは言えない。植物は六根に分かれる以前の「空」を「空」のまま感じる能力があるのだとすると、中枢神経の末端を肥大化させて脳を作り、その感覚を器官によって分化した動物たちは、植物よりも退化したのかもしれない。別の言い方をすれば、脳はつねに物事を固定化したがるのだ。人間の場合、4歳くらいで左右をつなぐ脳梁が完成するが、これは生物として生きていく無力なヒトが生きていく上で必要なものだったのではないだろうか。
モノの生滅、異同や「きれい」「汚い」という二元論的な概念は、大脳皮質によってつくられた戯論である。戯論を離れなければ、空なる実相を感じることはできない。
量子力学では、物質のミクロの様態を「粒子であり、また波である」とする。それは、「色であり、また空である」と同じである。人の脳はすぐに粒子化したがるが、二元論を避けて、一切を波動の変化として見ることもできる。「識」の傾向は、太古以来私たちの中に蓄積されてきているので、同種に属するヒトがおおよそ類似した現象を同じように認識できるのである。
「般若」とは、現実を二元論によらず、また概念にもよらず、直接につかむことである。18世紀の思想家ディビッド・ヒュームは、因果律が現象を生起させる原理なのではなく、それを解釈する上での強固な思考習慣であると言っているが、因果律とは、我々の脳のものの見方の性癖に他ならない。「いのち」が因果律に還元できない例として、アヒルの形成体をニワトリに埋め込んでも、水かきのないニワトリの足しか生えないということが挙げられる。つまり「全体性」との関係で、つねに何が形成されるのかが決まるのである。そこにあるのは、因果律を含む「異時」ではなく、「同時」あるいは「縁起」である。「般若」が実践される時、素粒子のあり方と同じように、因果を条件づける時間そのものは存在しない。
「いのち」の実感に反して、言葉が実体を分断し、文字化され、さらに確定づけていく。そうした科学で扱われる「知」とは別な「知」の様式である「般若」が対岸にある。言葉とは、老子や荘子、世尊にとっては、厄介極まりない、罪作りな道具なのである。「花」や「私」などは、言葉によって、もともとの「全体性」から切り離され、架空の自立性をもたされている。
「般若」とは、裸の「いのち」が本来もっている生命への気づきであり、「空」は「私」というものを抜きにした自性の本質的なあり方であり、それを感じる主体は自他の区別がつかない状態で「全体性」の中に溶け込んでいる。「般若」に近づくためには、意味を超えた音の響きが大事である。それが、意味を捉えようとする大脳皮質を飛び越えて、直接「いのち」に働くからである。咒文によって、私たちは植物のような根源的な感覚に回帰するであろう。普遍的な真理を理解し、記憶し、それを保つ力としての「陀羅尼」である「般若心経」を唱えるならば、「いのち」の響きのうちに少しずつ「私」を霧消させて、安らぎを感じることになるはずだ。(奥野克巳)